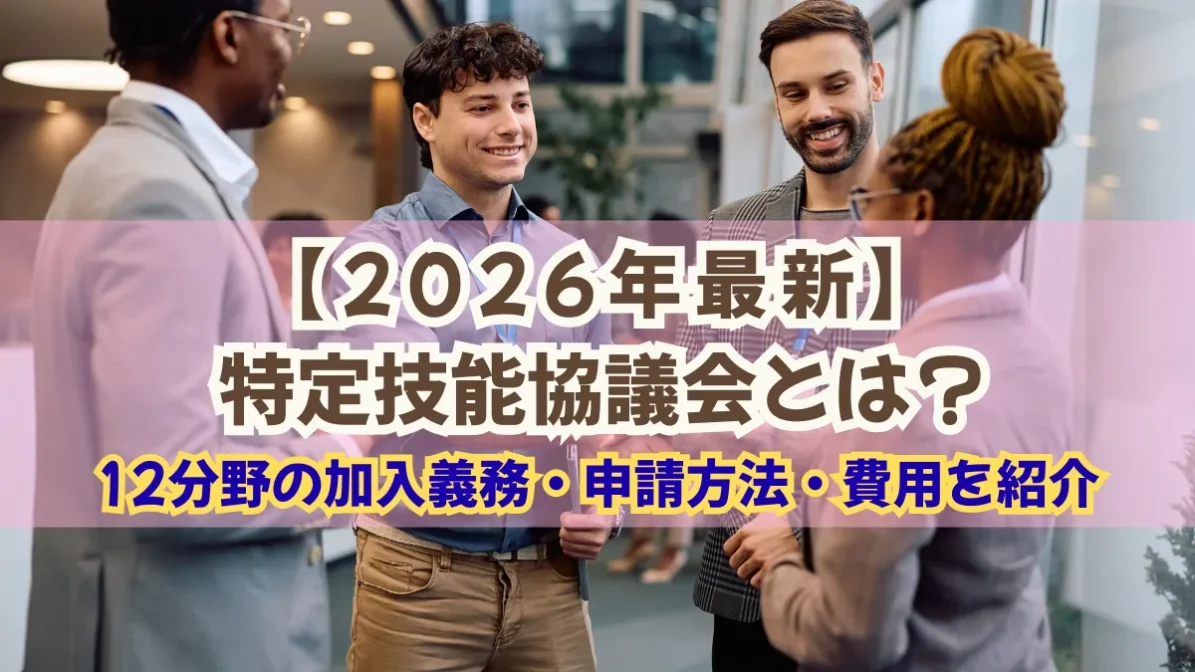特定技能外国人を受け入れる際に必ず加入が義務づけられている「特定技能協議会」。2024年6月15日の制度変更により、在留資格申請前の加入が必須となりました。
本記事では、協議会の役割から12分野別の加入方法、費用、手続きのタイミングまで、初めて特定技能外国人を受け入れる企業担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
- 特定技能協議会への加入義務と2024年6月の制度変更の内容
- 12分野別の協議会一覧と自社に該当する分野の確認方法
- 協議会への具体的な加入手続きの流れと在留資格申請までのスケジュール
1.特定技能協議会とは?制度の目的と企業が知るべき基本

協議会は特定技能制度の適正運用を支える公的機関
特定技能協議会とは、産業分野ごとに所管省庁が設置している公的機関です。
特定技能制度を適切に運用し、外国人材の適正な受け入れを実現するために設立されました。
協議会の構成員は以下の通りです。
- 受入れ機関(企業)
- 所管省庁
- 業界団体
- 登録支援機関
各産業分野の実情に応じた運営が行われており、例えば介護分野とビルクリーニング分野は厚生労働省、建設分野や航空分野などは国土交通省、農業や漁業などは農林水産省が担当しています。
協議会は、特定技能外国人を受け入れる企業と行政、業界団体が連携して情報を共有し、制度の円滑な運用を図るためのプラットフォームです。
協議会が担う6つの主な役割と活動内容
協議会は、特定技能制度の健全な運営のために以下の6つの役割を担っています。
| 役割 | 内容 |
| 制度・優良事例の周知 | 受け入れ企業に制度の最新情報を提供し、成功事例を共有 |
| 法令遵守の啓発 | 労働条件や生活支援について基準を守るよう指導 |
| 就業構造・経済情勢の分析 | 各産業分野の市場動向や技術革新の影響を分析 |
| 人手不足状況の把握 | 地域ごとの人材需要を把握し、受け入れ人数を調整 |
| 大都市圏集中の回避 | 地方での受け入れを促進する施策を協議 |
| 課題・情報の共有 | 受け入れ企業が直面する問題点を収集し制度改善につなげる |
必要に応じて、協議会は受入れ機関へ調査や指導を実施する権限も持っています。
受け入れ企業にとっての協議会の存在意義
受け入れ企業にとって、協議会は3つの重要な意義を持っています。
1. 在留資格申請の前提条件
2024年6月15日以降、協議会への加入は在留資格申請の必須要件です。協議会加入証明書がなければ、在留資格の申請そのものができません。
2. 受け入れ要件の事前確認機能
協議会の加入審査では、企業の事業内容が日本標準産業分類等に該当するか、特定技能外国人が従事する業務が禁止業務に該当していないかなどを事前にチェックします。加入申請が承認されることで、受け入れ要件を満たしていることの確認ができます。
3. 業界全体での健全な受け入れ体制の構築
協議会を通じて業界の受け入れ状況や課題が共有されることで、個々の企業だけでは解決困難な問題に業界全体で取り組むことができます。
協議会の加入申請は、在留資格申請前の重要なチェックポイントといえます。
特定技能1号の基本的な内容から取得要件まで、企業の人事担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。
2.協議会への加入は義務?知っておくべき法的要件

全ての受け入れ企業に加入が義務づけられている
協議会への加入は、特定技能外国人を受け入れる全ての企業に法的に義務づけられています。
例外は一切なく、すべての受け入れ企業は該当する産業分野の協議会構成員にならなければなりません。
加入義務の範囲
- 企業単位での加入が基本
- 分野によっては事業所単位での加入が必要
- 複数事業所で受け入れる場合は個別確認が必要
同一分野での2人目以降の受け入れ
同一分野で2人目以降の特定技能外国人を受け入れる場合、改めて協議会へ加入する必要はありません。
最初の受け入れで加入していれば、その加入が継続的に有効です。ただし、受け入れ人数に変更があった場合は協議会への届出が必要です。
建設分野の特殊性
建設分野は他の分野と異なり、建設業者団体が共同で設置する正会員団体に所属するか、賛助会員になることが求められます。会費の支払いも必要となります。
2024年6月15日の制度変更で何が変わったのか
2024年6月15日を境に、協議会への加入タイミングに関する重要な制度変更が実施されました。
| 項目 | 旧制度(2024年6月14日まで) | 新制度(2024年6月15日以降) |
| 加入タイミング | 受け入れ後4カ月以内 | 在留資格申請前 |
| 証明書提出 | 不要 | 必須 |
| 手続きの順序 | 受け入れ→協議会加入 | 協議会加入→在留資格申請 |
制度変更の背景
制度変更の背景には、以下のようなことがあります。
- 受け入れ企業が適切な要件を満たしているかを事前に確認するため
- 不適切な受け入れを未然に防ぐため
- 特定技能外国人の保護を強化するため
加入しない場合のリスクと罰則
協議会に加入しない、または加入が遅れた場合のリスクは以下の通りです。
協議会への加入は法的義務であることを十分に認識し、採用が決まったらすぐに手続きに着手しましょう。
3.いつまでに加入すべきか?申請タイミングの重要性

在留資格申請の前に加入を完了させることが必須
2024年6月15日の制度変更により、協議会への加入タイミングは「在留資格申請の前」が絶対条件となりました。
【手続きの正しい流れ】
この順序を守らなければ、在留資格の申請を受け付けてもらえません。
推奨は在留資格申請の3カ月以上前からの準備
実務的には、在留資格申請を予定している時期の3カ月以上前から協議会への加入準備を始めることを強く推奨します。
3カ月必要な理由
| 理由 | 内容 |
| 審査期間 | 申請から承認まで2週間~1カ月程度 |
| 書類不備のリスク | 初回申請時は不備が発生しやすく、差し戻しで追加期間が必要 |
| 申請集中期 | 年度末・年度初めは審査期間が延びる可能性 |
| 証明書発行期間 | 承認後、証明書発行や名簿登録に数日~1週間 |
初回申請の注意点としては、初めて特定技能外国人を受け入れる企業では、必要書類の準備に不慣れなため、記入漏れや添付忘れ、不適切な書類の提出などが頻繁に発生しやすいため、余裕をもって準備することをおすすめします。
余裕を持った申請スケジュールの立て方
協議会への加入をスムーズに進めるための推奨スケジュールは以下の通りです。
逆算スケジュールの例
| 時期 | 実施内容 |
| 在留資格申請予定日の3カ月前 | 必要書類のリストアップ開始、該当分野の確認 |
| 2.5カ月前 | 登記事項証明書など取得に時間がかかる書類の手配開始 |
| 2カ月前 | 雇用条件書、支援計画書の作成 |
| 1.5カ月前 | 全書類の最終確認、協議会への加入申請 |
| 1カ月前~申請日 | 協議会の審査、証明書取得、在留資格申請準備 |
具体例
在留資格申請を5月1日に行いたい場合
- 協議会加入申請: 3月初旬頃
- 採用決定からの準備開始: 2月中旬頃
特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業は、予想外のトラブルや遅延を前提に、さらに余裕を持ったスケジュール設定を心がけてください。
4.特定技能協議会12分野の完全一覧表

分野別の協議会名と所管省庁一覧
特定技能制度では、12の産業分野それぞれに協議会が設置されています。
【分野別・協議会名と所管省庁】
| 分野 | 協議会名 | 所管省庁 |
| 介護 | 介護分野における特定技能協議会 | 厚生労働省 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能協議会 | 厚生労働省 |
| 工業製品製造業 | 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 | 経済産業省 |
| 建設 | 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC) | 国土交通省 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
| 航空 | 航空分野特定技能協議会 | 国土交通省 |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能協議会 | 国土交通省 観光庁 |
| 農業 | 農業特定技能協議会 | 農林水産省 |
| 漁業 | 漁業特定技能協議会 | 農林水産省 水産庁 |
| 飲食料品製造業 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 |
| 外食業 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 |
ポイント
自社の事業がどの分野に該当するか確認する方法
協議会への加入申請前に、自社の事業がどの分野に該当するかを正確に判断する必要があります。
判断基準
- 日本標準産業分類との照合
- 総務省が定めている事業分類の基準
- 登記事項証明書の事業目的を確認
- 各協議会はこの分類に基づいて対象企業を判断
- 特定技能外国人が従事する業務内容
- 企業の主な事業が該当分野でも、業務が特定技能で認められているか確認
- 業務区分に含まれているかをチェック
複数事業を展開している企業の注意点
| ケース | 対応 |
| 製造業と販売業を両方実施 | 特定技能外国人を配置する部門に応じた分野を選択 |
| 製造部門で雇用 | 工業製品製造業分野 |
| 販売部門で雇用 | 該当する分野(飲食料品なら飲食料品製造業等) |
判断に迷った場合の対応
- 該当すると思われる分野の協議会の公式ウェブサイトを確認する
- 日本標準産業分類との対照表や具体的な業務例を確認する
- それでも判断が難しい場合は協議会事務局に直接問い合わせしてみる
事前確認に時間をかけても、正確な判断をすることが重要です。誤った分野に申請すると不受理となり、時間を大きくロスしてしまいます。
5.協議会加入の要件と必要書類の基本

全分野共通の基本的な加入要件
協議会への加入には、分野を問わず共通する基本要件があります。
【基本的な加入要件】
| 要件 | 内容 |
| 事業実態の証明 | 日本標準産業分類等に該当していることを示す |
| 受け入れ計画 | 業務内容、雇用条件、支援体制を示す |
| 適正な雇用条件 | 日本人と同等以上の報酬、労働関係法令の遵守 |
| 企業の適格性 | 法令違反の履歴がないこと、受け入れ能力があること |
主な提出書類
分野特有の要件も設定されています。
例えば、介護分野では介護事業所としての指定、ビルクリーニング分野では建築物清掃業等の登録が必要です。
分野別に異なる必要書類の概要
主要な分野の必要書類を整理しました。
【分野別主要必要書類】
| 分野 | 主な必要書類 |
| 介護 | 事業所指定通知書、雇用条件書、支援計画書、在留カード写し |
| ビルクリーニング | 建築物清掃業等の登録証明書、就業場所確認書面 |
| 工業製品製造業 | 製造品の画像・説明文、設備の画像・説明文、事業実態証跡(納品書等) |
| 建設 | 入会申込書、建設業許可証、履歴事項全部証明書、印鑑証明書 |
| 農業 | オンライン入力フォームに直接入力(郵送不要) |
| 飲食料品製造業・外食業 | 特定技能雇用契約届出書の写し、誓約書 |
それぞれの分野の特徴
介護分野の特徴
介護事業所としての指定を受けていることが前提条件です。雇用条件書と支援計画書は、出入国在留管理局へ提出した最新書類の写しを使用します。これらの書類は特定技能外国人ごとに準備が必要です。
ビルクリーニング分野の特徴
建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることの証明が必須です。特定技能外国人が実際に就業する場所を明確にする書面も求められます。
工業製品製造業分野の特徴
製造業という性質上、実際に製造活動を行っていることを視覚的に証明する必要があります。製造品や設備の画像提出が特徴的で、直近1年以内の納品書や出荷指示書などの事業実態を示す証跡も必要です。
建設分野の特徴
他分野と異なり、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入という形になります。建設業許可を受けていることが前提で、正会員団体に所属するか賛助会員になるかで必要書類が変わります。年会費の支払いも必要です。
農業分野の特徴
完全オンライン申請で、書類の郵送は基本的に不要です。農業特定技能協議会の専用フォームに必要情報を直接入力するだけで手続きが完結します。他分野に比べて申請が簡便です。
飲食料品製造業・外食業分野の特徴
両分野は同じ食品産業特定技能協議会を共同設置しています。誓約書の提出が求められ、総合スーパーマーケットや食料品スーパーマーケットで受け入れる場合は追加の誓約書が必要です。特定技能外国人が未定でも申請可能な点が特徴です。
詳細な必要書類リストは、各協議会の公式ウェブサイトに掲載されています。申請前に必ず最新情報を確認しましょう。
オンライン申請と郵送申請の違い
協議会への加入申請方法は分野によって異なります。
【申請方法一覧】
| 申請方法 | 対象分野 | 特徴 |
| オンライン | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業 | 24時間申請可能、郵送不要、状況確認がしやすい |
| 郵送 | 造船・舶用工業、自動車整備 | 書類を協議会事務局や地方運輸局に郵送 |
| 電子メール | 航空 | メールで提出(困難な場合は郵送可) |
| 特殊 | 建設 | 正会員団体は各団体の方法、賛助会員はオンライン |
【オンライン申請の流れ】
郵送申請の注意点
- 簡易書留や特定記録郵便の利用を推奨
- 書類の到着から審査開始までにタイムラグあり
いずれの方式でも、申請前に必要書類の確認を徹底し、記入漏れや添付忘れがないよう注意することが重要です。
6.【分野別】協議会の入会方法と手続きの流れ

厚生労働省管轄2分野の入会方法
厚生労働省が管轄する介護分野とビルクリーニング分野は、いずれもオンライン申請に対応しています。
介護分野
- 運営:公益社団法人国際厚生事業団
- 申請方法⇒専用ウェブサイトからオンライン申請
- 必要書類
- 事業所の指定通知書
- 事業所の概要書等
- 雇用条件書
- 1号特定技能外国人支援計画書
- 在留カード写し
※雇用条件書と支援計画書は出入国在留管理局へ提出した最新書類の写しを使用
※外国人ごとに準備が必要
ビルクリーニング分野
- 申請方法⇒オンライン申請フォーム
- 必要書類
- 建築物清掃業等の登録証明書の写し
- 就業場所が確認できる書面の写し
- その他必要な書面
- 前提条件:ビルクリーニング業としての正式な登録
審査期間は通常2週間~1カ月程度です。
経済産業省管轄・工業製品製造業の入会方法
工業製品製造業分野
- 名称:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
- 申請方法⇒専用ポータルサイトを通じた申請
必要書類の特徴: 製造実態を詳細に証明する必要があります。
| 書類 | 内容 |
| 製造品の画像と説明文 | 実際に製造している製品 |
| 完成品の画像と説明文 | 製造品が組み込まれる最終製品 |
| 設備の画像と説明文 | 工作機械、鋳造機、鍛造機、プレス機等 |
| 事業実態の証跡 | 直近1年以内の納品書、出荷指示書、仕入書等 |
| 請負契約書の写し | 請負による製造の場合のみ |
【申請手順】
◆証明書について◆
証明書は発行されず、構成員名簿(ウェブサイト掲載)への登録をもって証明とします。名簿は定期的に更新され、在留資格申請時にこの名簿を利用します。
国土交通省管轄5分野の入会方法
国土交通省は5分野を管轄しており、分野ごとに申請方法が異なります。
建設分野(一般社団法人JAC)
建設分野のみ特殊な仕組みで、年会費と受入れ負担金の支払いが必要です。
| 加入方法 | 年会費 | 受入れ負担金 |
| 正会員団体の会員 | 36万円 | 月額12,500円/人 |
| 正会員団体所属 | 各団体が定める会費 | 月額12,500円/人 |
| 賛助会員 | 24万円 | 月額12,500円/人 |
【申請方法】
- 正会員団体の会員:所属団体の方法に従う
- 賛助会員:JACの公式ウェブサイトからオンライン申請
【必要書類】
造船舶用工業分野
- 申請方法⇒郵送
- 提出先:国土交通省海事局船舶産業課
- 事前確認が必要:まず様式第1号で事業者確認を受ける
- 必要書類
- 様式第1号:造船・舶用工業事業者の確認申請書
- 様式第5号:協議会の加入申請書
- 登記事項証明書(個人事業主は開業届)
自動車整備分野
- 申請方法⇒郵送
- 提出先:各地方運輸局または沖縄総合事務局
- 必要書類:協議会第1号様式「協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」
- 注意:自社の事業所を管轄する地方運輸局に提出
航空分野
- 申請方法⇒電子メール(困難な場合は郵送)
- 提出先:国土交通省航空局 協議会事務局
- 必要書類:加入届出書
宿泊分野
- 申請方法⇒オンライン
- 申請先:e-Gov電子申請サイトまたは宿泊技能人材ポータル
- 前提条件:旅館業法に基づく許可
- 管轄:国土交通省観光庁
農林水産省管轄4分野の入会方法
農林水産省は4分野を管轄しています。
農業分野
- 申請方法⇒完全オンライン
- 申請フォーム:「農業特定技能協議会入会申込みフォーム」
- 特徴:書類の郵送不要、全ての手続きがウェブ上で完結
- 通知:登録メールアドレスに「加入通知書」が送付
漁業分野
- 申請方法⇒2号構成員経由
- 提出先:所属する漁業協同組合などの2号構成員
- 必要書類
- 加入申請書
- 在留申請の関係書類の写し
- 協議会の協議事項に関する措置を講じていることの証明書類
- その他基準適合を証明できる書類
- 注意:正しい2号構成員に申請しないと不受理
飲食料品製造業・外食業分野(食品産業特定技能協議会)
【必要書類】
- 特定技能雇用契約に係る届出書の写し
- 飲食料品製造業分野または外食業分野の誓約書
- (該当する場合)スーパーマーケットにおける特定技能外国人の業務に関する誓約書
重要な注意点
- 飲食料品製造業と外食業の両方で受け入れる場合、それぞれ加入申請が必要
- 既にどちらか一方で構成員でも、別分野では改めて審査を受ける
- 特定技能外国人が未定でも申請可能(氏名等は未記入で提出可)
各分野とも、申請方法や必要書類は変更される可能性があるため、申請前に必ず各協議会の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。
7.協議会加入証明書と在留資格申請の関係

なぜ協議会加入証明書が在留資格申請に必須なのか
協議会加入証明書が在留資格申請の必須書類とされている理由は明確です。
必須とされる理由
| 理由 | 内容 |
| 要件の事前確認 | 受け入れ企業が基本要件を満たしているかを確認 |
| 不適切な受け入れの防止 | 事前審査により問題を未然に防ぐ |
| 外国人材の保護強化 | 適正な受け入れ体制の確保 |
| 連携体制の構築 | 企業・行政・業界団体の連携を促進 |
2024年6月15日の制度変更により、協議会加入証明書は在留資格認定証明書交付申請の際に提出しなければならない書類となりました。
この書類がなければ、出入国在留管理局は申請を受理しません。
協議会加入審査で確認される内容
- 企業の事業内容が該当分野に適合しているか
- 特定技能外国人が従事する業務が認められている業務区分か
- 適切な雇用条件や支援体制が整っているか
つまり、協議会への加入承認は、受け入れ企業が基本的な要件を満たしていることの証明になります。
証明書の発行方法と分野別の違い
協議会加入証明書の発行方法は、分野によって2つのパターンに分かれます。
【証明方法の比較】
| 方式 | 内容 | 対象分野例 |
| 証明書発行方式 | 協議会が正式な証明書を発行 | 介護、建設など |
| 構成員名簿方式 | ウェブサイト掲載の名簿で証明 | 工業製品製造業など |
証明書発行方式
- 加入承認後、協議会事務局に証明書発行を依頼
- 証明書には企業名、所在地、加入承認日、外国人情報等を記載
- 発行期間:数日~1週間程度
- 在留資格申請時に他の書類と一緒に提出
構成員名簿方式
- 協議会の公式ウェブサイトに構成員名簿を掲載
- 証明書の発行なし
- 在留資格申請時に名簿のページを印刷またはPDFで提出
- 名簿は定期的に更新されるため、必ず最新版を使用
【注意点】
- 古い名簿を使用すると自社が掲載されていない可能性あり
- 在留資格申請の直前に最新版をダウンロードしておく
- 名簿の更新日も必ず確認しておく
どの方法で証明するかは各分野の協議会によって異なるため、加入承認時に確認しておきましょう。
加入申請から証明書取得までの流れ
協議会への加入申請から在留資格申請までの一連の流れを整理します。
【手続きの全体フロー】
| ステップ | 内容 | 所要期間 |
| 1. 必要書類の準備 | 該当分野の確認、必要書類のリストアップと収集 | 1~2週間 |
| 2. 協議会への加入申請 | オンライン・郵送・メールで申請 | 1日 |
| 3. 協議会による審査 | 事業内容の適合性、書類の完備等を確認 | 2週間~1カ月 |
| 4. 加入承認と証明書取得 | 承認通知、証明書発行または名簿登録確認 | 数日~1週間 |
| 5. 在留資格申請 | 協議会証明書を含む書類一式で申請 | – |
ステップ3:協議会による審査の詳細
ステップ4:加入承認と証明書取得の詳細
【証明書発行方式の場合】
- 審査完了後、承認通知が届く
- 証明書発行を依頼
- 数日~1週間で証明書入手
【構成員名簿方式の場合】
- 審査完了後、承認通知が届く
- 数日待って名簿に登録
- 最新名簿をダウンロード・確認
全体の所要期間について
採用決定から在留資格申請まで、最低でも2~3カ月、余裕を持たせるなら3~4カ月程度の期間を見込む必要があります。
逆算してスケジュールを立て、計画的に手続きを進めましょう。
8.特定技能外国人の受け入れから協議会加入までの実務フロー

ステップ1:特定技能外国人の採用決定
特定技能外国人の採用活動を行い、雇用する人材が決まった段階が出発点です。
【この段階で確認すべき事項】
| 確認項目 | 内容 |
| 要件の充足 | 特定技能評価試験と日本語試験の合格、または技能実習2号の良好な修了 |
| 在留資格 | 現在の在留資格の種類と在留期限 |
| 業務内容 | 特定技能制度で認められている業務区分に該当しているか |
| 雇用条件 | 日本人と同等以上の報酬、適切な労働時間・休日 |
採用候補者と雇用条件について合意し、雇用契約を結ぶ方向で話が進んだ時点で、すぐに協議会への加入準備を開始します。
重要: 採用候補者と雇用契約を結ぶ方向で話が進んだ時点で、すぐに次のステップへ進みましょう。「正式決定してから」と待っていると、受け入れが大幅に遅れます。
ステップ2:自社の該当分野と協議会の特定
採用が決まったら、自社の事業がどの分野に該当するかを正確に判断します。
【分野判断の3ステップ】
| 順序 | やること | 確認内容 |
| 1 | 登記事項証明書をチェック | 事業目的を確認 |
| 2 | 日本標準産業分類と照合 | 総務省が定める分類と照らし合わせる |
| 3 | 業務内容で最終確認 | 特定技能外国人が実際に行う業務内容で判断 |
重要: 間違った分野に申請すると不受理になり、時間を大幅にロスします。不安な場合は必ず事前に確認しましょう。
ステップ3:必要書類の準備と加入申請
該当分野が決まったら、その分野で求められる書類を集めます。
【必要書類は2種類】
| 書類の種類 | 具体例 | 入手方法 |
| 企業に関する書類 | ・登記事項証明書 ・営業許可証 ・事業概要書 ・分野特有の許認可証明書 | 法務局、許認可を受けた役所など |
| 外国人に関する書類 | ・雇用条件書 ・支援計画書 ・在留カード写し | 自社で作成、外国人本人から入手 |
書類作成のチェックリスト
【申請方法の確認】
| 申請方法 | 対象分野 | やり方 |
| オンライン | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業 | 専用サイトで入力、PDFをアップロード |
| 郵送 | 造船・舶用工業、自動車整備 | 簡易書留で協議会事務局へ送付 |
| メール | 航空 | 書類をメールに添付して送信 |
ステップ4:協議会による審査と承認
申請後は協議会が内容を審査します。この期間は待ちの時間です。
【審査の流れ】
| タイミング | 何が起こるか | やること |
| 申請直後 | 協議会が書類を受理 | 受理確認メールや受付番号を保管 |
| 審査中(2週間~1カ月) | 事業内容や書類の確認 | 協議会からの連絡を待つ |
| 不備がある場合 | 協議会から電話・メールで連絡 | すぐに対応、追加書類を提出 |
| 審査完了 | 承認通知が届く | 次のステップへ進む |
審査で確認されること
重要:協議会から連絡があった場合は、できるだけ早く対応してください。対応が遅れると、その分だけ審査期間が延びてしまいます。
ステップ5:協議会加入証明書の取得
審査に合格したら、在留資格申請に必要な証明書を入手します。
【証明書の種類は分野によって2パターン】
| パターン | 内容 | 対象分野例 | やること |
| A:証明書発行 | 協議会が正式な証明書を発行してくれる | 介護、建設など | 協議会に証明書発行を依頼する |
| B:名簿掲載 | ウェブサイトに名前が載る | 工業製品製造業など | ウェブサイトの名簿をダウンロード |
パターンA:証明書発行方式の流れ
- 承認通知を受け取る
- 協議会に証明書発行を依頼する
- 数日~1週間待つ
- 証明書が届く(郵送またはPDF)
- 大切に保管(在留資格申請で使用)
パターンB:名簿掲載方式の流れ
- 承認通知を受け取る
- 数日~1週間待つ
- 協議会ウェブサイトで名簿更新を確認する
- 最新の名簿をダウンロードする
- 自社の名前があることを確認する
- 印刷またはPDF保存する(在留資格申請で使用)
注意点
- 名簿は定期的に更新されるので、必ず最新版を使う
- 古い名簿だと自社の名前が載っていないことがある
- 在留資格申請の直前に最新版を取得するのがベスト
ステップ6:在留資格認定証明書交付申請
協議会加入証明書を手に入れたら、いよいよ在留資格の申請です。
【在留資格申請に必要な主な書類】
| 書類カテゴリ | 主な書類 |
| 協議会関連 | 協議会加入証明書または構成員名簿の写し |
| 申請書類 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
| 外国人関連 | 履歴書、資格証明書、パスポート写し |
| 雇用関連 | 雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書 |
| 企業関連 | 企業概要書、財務状況証明書類 |
【申請方法】
- 地方出入国在留管理局に直接持参
- 郵送申請
- オンライン申請(システム導入されている場合)
【審査期間】
通常1~3カ月
【証明書交付後の流れ】
- 在留資格認定証明書が交付される
- 証明書を海外の特定技能外国人に送付
- 外国人が日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザ発給後、日本に入国
全体の所要期間は採用決定から受け入れまで、全体で3~6カ月程度の期間が必要です。計画的に手続きを進めることが重要です。
特定技能1号と2号の違い、対象となる職種の詳細、そして企業が外国人労働者を受け入れる際の手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。
8.協議会加入で特定技能外国人のスムーズな受け入れを実現
特定技能協議会への加入は法的義務であり、在留資格申請の前提条件です。
2024年6月15日以降、受け入れ前の加入が必須となったため、採用決定後すぐに手続きを開始しましょう。
在留資格申請の3カ月以上前からの準備が推奨されます。自社の該当分野を正確に判断し、必要書類を揃えて早めに申請することで、トラブルなく外国人材の受け入れを実現できます。