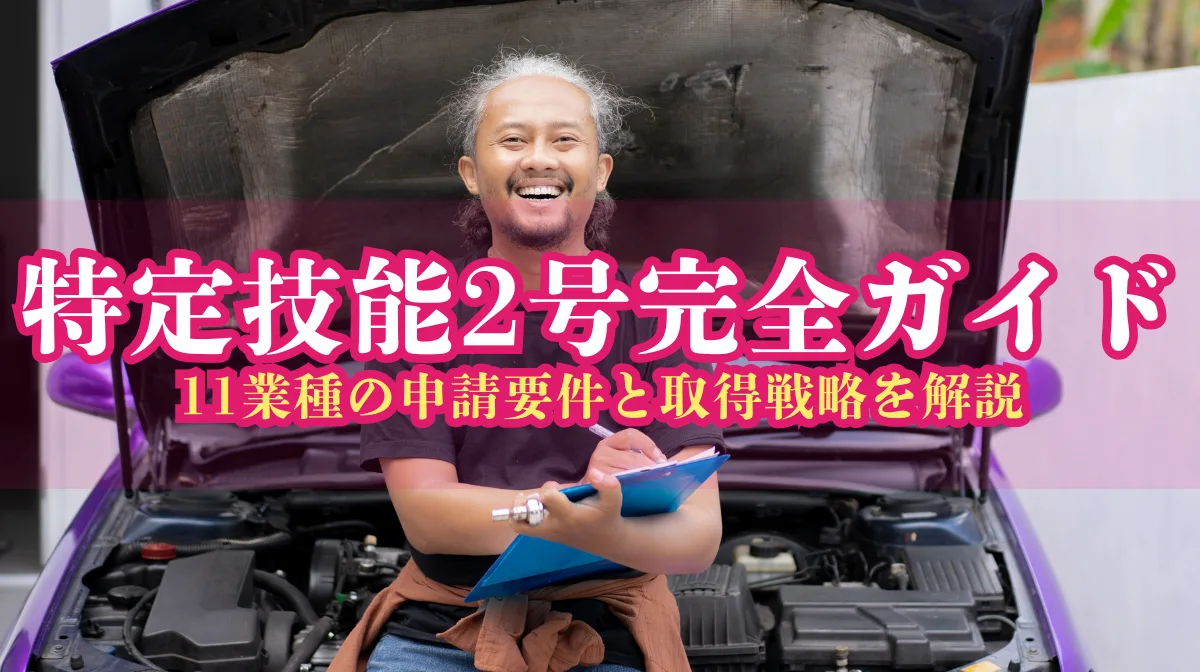深刻化する人手不足を背景に、2019年4月に創設された在留資格「特定技能1号」。
介護や建設など12の産業分野で外国人材の受け入れが可能なこの制度は、多くの企業の人材確保の選択肢として注目されています。
本記事では、特定技能1号の基本的な内容から取得要件まで、企業の人事担当者が知っておくべき重要なポイントを解説します。
- 特定技能1号の対象分野と具体的な在留期間・更新条件
- 技能実習からの移行制度や日本語能力要件など、採用に向けた実務的な要件
- 特定技能2号との違いと、それぞれの制度の特徴
1.特定技能1号とは

「特定技能1号」は、深刻化する人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格です。
従来の技能実習制度とは異なり、即戦力となる外国人材の受け入れを主目的としており、介護や建設など特定の16分野で活用できます。
制度の基本的な枠組みと重要なポイントを見ていきましょう。
対象となる産業分野
特定技能1号は、16の産業分野で外国人材の受け入れが可能となっています。




これらの分野は人手不足が特に深刻な産業として選定されており、介護、建設、飲食料品製造業などが含まれています。各分野では、その業界特有の技能試験が設けられています。
在留期間と更新の条件
特定技能1号の在留期間は1年、6カ月、4カ月のいずれかで更新が可能です。ただし、通算で5年が上限と定められています。
在留期間は在留カードに記載され、期限内に更新手続きが必要です。
在留期間の通算方法と計算の注意点
通算5年の計算において、以下の重要なポイントがあります。
- 通算開始日:在留カードを受け取った日(特定技能として入国した日)
- 雇用開始日は通算開始日ではないので注意が必要
以下の期間は特定技能1号の通算5年に含まれます。
- 産業分野・業務区分が変更になった期間
- 転職時の前職での特定技能就労期間
- 一時帰国期間(例外あり)
- 産前産後休暇、育児休暇
- 失業期間
- 労働災害による休業期間
- 再入国許可による出国期間
求められる日本語能力
特定技能1号では、日常会話レベルの日本語能力が求められます。具体的には、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上など、定められた試験での合格が必要です。
ただし、技能実習2号を修了している場合は、日本語試験が免除されます。
参考:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト 日本語能力試験 JLPT
在留期間満了後の選択肢
特定技能1号の通算5年が経過した後も、日本での就労を継続するための選択肢があります。
より高度な技能を持つ人材として特定技能2号への移行を目指すことができるほか、技術・人文知識・国際業務ビザの取得という道もあります。
介護分野で働く場合は、介護福祉士の資格を取得することで別の在留資格に移行することが可能です。また、日本人または永住者の配偶者となることで、在留資格を変更するというケースも選択肢のひとつです。
ただし、これらの選択肢はいずれも厳格な条件が設けられており、要件を満たすための十分な準備と計画が必要です。企業としては、従業員の将来的なキャリアパスを見据えた支援を検討する必要があるでしょう。
特定技能1号が創設された背景
特定技能1号の創設は、日本の深刻な人手不足に対応するために行われました。
それ以外の背景として、
- 出生率低下による少子高齢化の進行
- 既存の外国人労働者受け入れ制度の限界
- 外国人労働者受け入れの円滑化
- 法改正による制度整備
などがあります。
このような背景のもと、日本政府は「特定技能1号」を創設し、適切な外国人労働者の受け入れを進めているのです。
従来の技能実習制度では、技能移転による国際貢献が主目的でしたが、特定技能1号では、即戦力となる外国人材の受け入れを明確に目的としています。
特定技能制度における1号の位置づけ
特定技能制度は1号と2号に分かれており、1号は基礎的な技能を持つ人材の受け入れを想定しています。
単純労働をメインにはできませんが、一定の技能と日本語能力があれば、幅広い業務に従事することができるものです。
2.特定技能2号との違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、在留期間や家族帯同、求められる技能水準など、重要な違いがいくつか存在します。
企業が外国人材の長期的な活用を検討する上で、この違いを理解することは非常に重要です。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | ・通算5年まで ・1年、6カ月、4カ月ごとの更新 | ・上限なし ・3年、1年、6カ月ごとの更新 ・実質的な永住が可能 |
| 家族帯同 | ・原則として認められない ・配偶者・子どもの帯同は不可 | ・条件を満たせば可能 ・配偶者と子どもに在留資格付与 ・家族での日本生活が可能 |
| 求められる技能水準 | ・「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」レベル ・指導者の指示・監督のもとでの業務遂行 ・基本的な業務の独力での遂行が可能 | ・「熟練した技能」レベル ・他の技能者への指導が可能 ・工程管理など、責任ある業務の遂行が可能 |
特定技能2号についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事でご紹介しています。
3.特定技能1号の取得要件とは?

特定技能1号の取得には、主に「技能試験」と「日本語能力試験」の合格が必要です。また、技能実習2号からの移行という方法もあり、その場合は試験が免除されるケースもあります。
ここでは、それぞれの取得ルートと具体的な要件について詳しく解説していきます。
技能試験と日本語能力試験の合格
特定技能1号の取得には、原則として以下の2つの試験に合格する必要があります。
- 分野別の技能試験
- 日本語能力試験(JFT-Basic A2以上、またはJLPT N4以上)
1つ目は16分野それぞれに設けられた技能試験で、分野ごとに必要な技能レベルを測定します。
例えば造船・舶用工業分野分野であれば「造船・舶用工業分野特定技能1号試験」に合格しなければなりません。
2つ目は日本語能力の確認試験で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上のいずれかが必要です。
ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、これらの試験が免除される場合もあります。
試験実施のスケジュールは分野によって異なり、国内外で定期的に開催されています。
参考:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト 日本語能力試験 JLPT
技能実習からの移行
技能実習2号を良好に修了した外国人が特定技能1号への移行を希望する場合、以下の条件で特定技能1号へ移行することができます。
- 技能実習の職種と特定技能で従事する業務に関連性があること
- 技能実習を良好に修了していること
特に、技能実習を3年間良好に修了した場合は、技能試験と日本語試験が免除されるという大きなメリットがあります。なお、技能実習と異なる業務に就く場合でも、2号修了者は日本語試験が免除されます。
申請に必要な書類と手続き
特定技能1号の申請には、大きく分けて3種類の書類が必要です。
| 書類の種類 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 申請人に関する書類 | ・在留審査申請書(証明写真付き) ・雇用契約書(様式V) ・技能試験・日本語能力試験の合格証 ・社会保険料の納付記録 など |
| 雇用企業に関する書類 | ・会社概要(資本金、年間売上等) ・財務・コンプライアンス関係書類 ・支援計画関連書類 ・登録支援機関との契約書(委託する場合) など |
| 産業分野別の書類 | ・認定申請書(分野別) ・企業の誓約書 ・その他分野固有の必要書類 など |
書類は原則としてA4用紙に片面印刷で提出する必要があります。
上記に書かれた書類はあくまで基本的な書類の種類になります。特定技能1号の申請に必要な書類は、申請人や受け入れ機関の状況、従事する分野によって異なるため、事前に出入国在留管理局のウェブサイトで最新情報を確認することをお勧めします。
4.特定技能1号の特徴的な制度

特定技能1号には、他の在留資格にはない独自の制度的特徴がいくつかあります。特に「外国人支援」に関する規定は重要で、受入れ企業には様々な義務が課されています。
ここでは、企業が必ず押さえておくべき制度的な特徴と実務上の注意点を解説します。
外国人支援計画の必要性
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業には、充実した支援体制の整備が義務付けられています。この支援体制は以下の要件を満たす必要があります。
| 支援体制の要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 支援責任者・担当者の選任 | ・過去2年間の中長期在留者の受入実績がある企業は役職員から選任 ・外国人が理解できる言語での支援が可能な体制 ・定期的な面談実施体制の整備 |
| 支援計画の策定 | ・日本語と外国人の理解可能な言語の2通りで作成 ・支援内容や業務委託範囲を明記 ・外国人本人への写し交付が必須 |
| 文書管理体制 | ・支援状況に関する文書作成 ・雇用契約終了後1年以上の保管義務 ・支援の実施状況を記録・保存 |
特に重要なのは、支援責任者と支援担当者の選任です。これらの担当者は、外国人材の生活相談から在留管理まで、包括的なサポートを提供する必要があります。
なお、支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することもできます。この場合、委託内容を明確にした契約を締結し、適切な支援体制が維持されていることを定期的に確認が必要です。
支援計画には、
- 入国前の生活ガイダンス
- 住宅確保
- 生活オリエンテーション
- 各種行政手続きの支援
など、具体的な支援内容を明記する必要があります。また、在留期間中の継続的な支援として、日本語学習の機会提供や相談・苦情対応体制の整備も求められます。
登録支援機関の役割
過去2年間に外国人材の受入れ実績がない、生活相談に従事した役員や職員がいない企業は、特定技能所属機関(受け入れ機関)の要件を満たせません。
また、支援責任者・支援担当者についても、直近の2年間に外国人労働者の生活相談業務に従事した経験が必要です。
そのため、要件を満たせない企業については登録支援機関に支援業務を委託する必要があります。
登録支援機関は、受入れ企業に代わって特定技能外国人への支援を行う、出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関です。
以下が主な役割と要件です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な役割 | ・外国人材への生活支援全般 ・在留手続きのサポート ・各種相談対応 ・行政機関への届出代行 |
| 支援体制要件 | ・支援責任者と1名以上の支援担当者の配置 ・外国人が理解できる言語での対応体制 ・2年以上の外国人支援実績 |
| 重要な義務 | ・適切な支援の実施と記録 ・出入国在留管理庁への定期報告 ・支援費用の外国人への転嫁禁止 |
企業が自社で支援体制を整えることが難しい場合、登録支援機関に支援業務を委託することで、専門的かつ効率的な支援体制を確保できます。
ただし、支援計画自体の作成は企業の責任で行う必要があり、登録支援機関はその作成についてアドバイスを提供する立場でしかありません。
なお、これらの業務を怠った場合、登録支援機関は登録取り消し処分となる可能性があることに留意しましょう。
支援業務は企業が直接行うこともできますが、登録支援機関に委託することも可能です。支援が適切に行われない場合、企業の受け入れ資格が取り消されるリスクがあるため、万全な体制を整えることが重要です。
登録支援機関についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
■登録支援機関への委託を検討されているなら…
1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。
技能実習からの移行制度
技能実習2号修了者は、試験免除で特定技能1号に移行できる制度があります。これにより、すでに日本での就労経験のある人材を円滑に受け入れることが可能です。
手続きは、技能実習から継続して特定技能1号に移行する場合は在留資格変更許可申請を、一度帰国してから再度来日する場合は在留資格認定証明書交付申請を行います。
企業にとっては、日本での就労経験があり、即戦力となる人材を確保できる有効な制度といえます。
5.特定技能1号の今後の展望

2019年の制度創設から約6年が経過し、特定技能1号の利用は着実に増加しています。
2025年1月現在、制度の運用状況や社会のニーズに応じた見直しも進んでおり、今後さらなる変化が予想されます。
ここでは、現在の利用状況と今後の展望について解説します。
制度の利用状況と実績
特定技能1号の制度は、2019年4月の創設以降、着実に利用者数を増やしています。
出入国在留管理庁の発表によると、5年間における受け入れ見込み人数目標は345,150人とされており、令和6年6月末時点での在留者数は251,747人と、目標の約7割の人口です。
特に介護、建設、飲食料品製造業などの分野で活用が進んでいます。2025年1月現在、多くの企業が人材確保の選択肢として検討しています。
受入れ企業の規模も多様化しており、大企業から中小企業まで、幅広い企業で活用されています。特に地方の中小企業では、人手不足解消の切り札として、積極的な採用を進めているケースが増えています。
目標人数達成まであと約9万人という状況ですが、技能実習からの移行促進や受入れ要件の緩和など、政府による制度改善の取り組みにより、今後さらなる在留者数の増加が期待されるでしょう。
企業の採用ニーズと外国人材のキャリア形成の両面で、この制度は重要な役割を果たしていると評価されているのです。
今後予想される制度の変更点
特定技能1号制度は、社会のニーズや運用状況に応じて継続的な見直しが行われています。そのような背景から2025年以降、以下のような制度変更が予想されます。
受入れ分野の拡大
- 人手不足が深刻化する新たな産業分野への適用拡大
- 既存分野における職種の追加
在留要件の見直し
- 技能試験や日本語能力試験の要件緩和の検討
- 技能実習からの移行要件の簡素化
支援体制の強化
- オンラインを活用した支援方法の導入
- 登録支援機関の役割拡大と要件の明確化
特に注目されるのは、技能実習制度から「育成就労制度」への移行に伴う制度改正です。これにより、特定技能1号への移行パターンも変化する可能性があります。
また、デジタル化の進展に対応した新しい在留管理・支援の仕組みの導入も今後検討されるかもしれません。
6.特定技能1号が切り開く人材活用の新時代
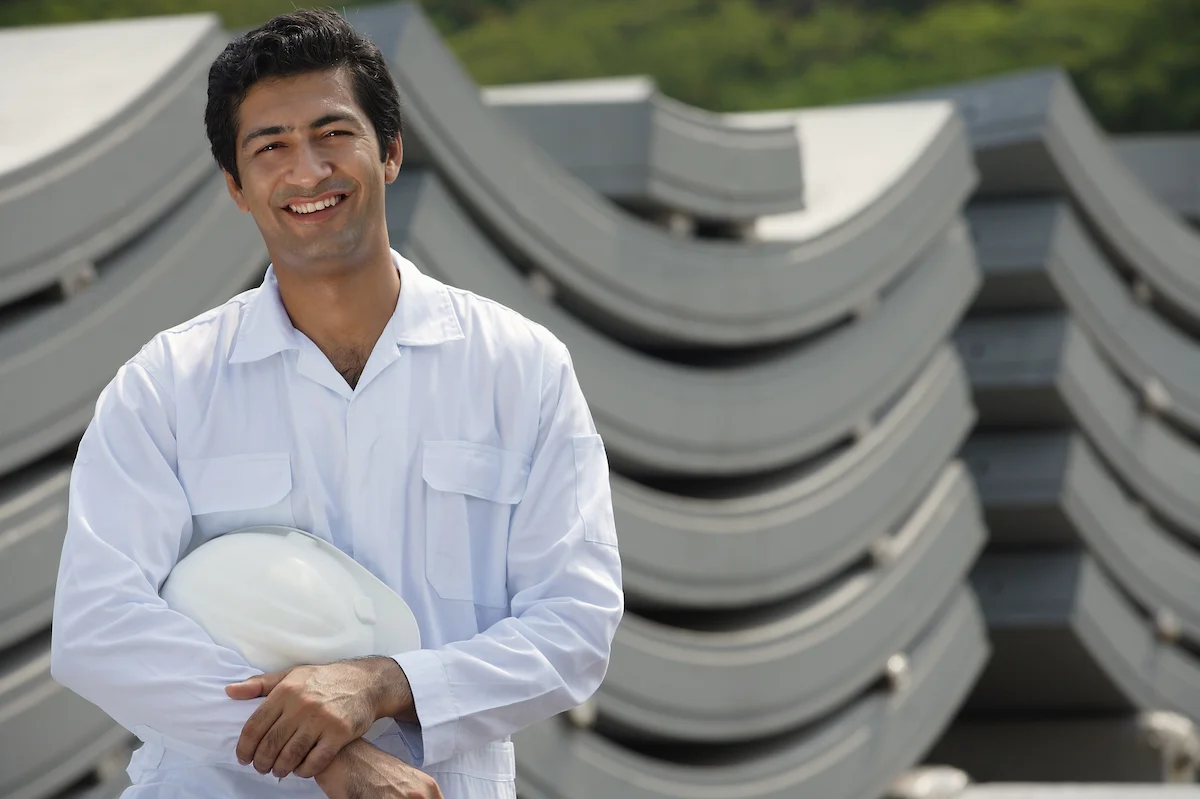
特定技能1号は、即戦力となる外国人材の受け入れを可能にする重要な制度です。
5年という在留期限や家族帯同の制限はあるものの、技能実習からの移行や特定技能2号へのステップアップなど、柔軟な活用が期待されます。
企業の実情に合わせて制度を理解し、計画的な人材確保・育成に活用することが、これからの企業成長の鍵となるでしょう。