特定技能外国人の採用を検討する中で、「登録支援機関への委託は必要?」「費用はどのくらい?」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
実は、登録支援機関の活用は、企業規模や受入れ経験によって選択肢が変わってきます。
本記事では、登録支援機関の役割から選び方まで、実務経験豊富な専門家の視点で、成功する外国人採用のポイントを解説します。
- 登録支援機関に委託すべき業務と自社で対応可能な業務の見分け方
- 企業の状況に応じた登録支援機関の選び方と適正な費用相場
- 外国人受入れを成功に導くための支援機関との効果的な連携方法
1.登録支援機関とは?特定技能外国人の受入れに必須の理由と役割

特定技能制度において、登録支援機関は企業と外国人材の橋渡し役として重要な存在です。
なぜ支援が必要なのか、どのような役割を果たすのか、制度の基本から支援を受けるメリットまで、登録支援機関の全体像について詳しく見ていきましょう。
登録支援機関ができること・監理団体との違いを解説
登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する企業に代わって外国人の支援を行う機関です。
出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者で、支援体制が整った業界団体、民間法人、行政書士、社労士など、さまざまな事業者が活動しています。
監理団体と混同されやすいのですが、監理団体は技能実習生を支援する団体であり、特定技能外国人の支援を行う登録支援機関とは異なります(ただし、監理団体が登録支援機関として登録している場合もあります)。
参考:外国人技能実習機構
特定技能制度で支援が必要な理由
特定技能制度において、外国人を受け入れる企業(受入れ機関)には、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています。
これは単なる規則ではありません。支援内容は専門的な知識が必要な手続きから、日常生活のサポートまで多岐にわたります。
これらを自社だけですべての支援を行うことは多くの企業にとって負担が大きいのが現状なのです。
支援機関に頼むとどんなメリットがあるの?
登録支援機関に支援を委託する主なメリットは以下の3つです。
| 登録支援機関に委託するメリット | 詳細 |
|---|---|
| 外国人材への業務指導に専念できる | 様々な支援業務を外部に任せることで、本来の目的である業務指導に注力できます |
| 支援にかかる手間を大幅に削減 | 数時間のガイダンスや各種手続きなど、時間のかかる業務を任せられます |
| 第三者機関として客観的な立場でサポート | 職場の上司や同僚には相談しづらい悩みも、第三者機関だからこそ相談しやすく、潜在的なトラブルの早期発見にもつながります |
2.登録支援機関に委託できる業務内容
登録支援機関に委託できる業務は多岐にわたります。
どのような支援が必要で、どの程度の費用がかかるのか。実際の支援内容と費用感について、具体的に解説していきます。
必ず実施しなければならない支援業務の内容
登録支援機関が行う義務的支援には以下の10項目があります。


事前ガイダンス
事前ガイダンスの実施時間は1~3時間が目安です。
1時間に満たない場合は事前ガイダンスを行ったとはいえない、と運用要領に明示されていることに留意してください。
そして対面またはテレビ通話での実施が必須であるため、メールや文書を送りつけて読ませただけでは事前ガイダンスを行ったとは認められません。
事前ガイダンスでは以下の内容の説明が行われます。
- 業務内容や報酬額などの労働条件の説明
- 日本で行える活動範囲
- 入国にあたって必要な手続き
- 保証金の支払いや違約金に係わる契約を現時点でしていないこと、そして今後もしてはいけない、ということの確認
- 入社準備費用や取次機関への支払いは、内容と金額を了承しているかの確認
- 支援費用は特定技能外国人に負担させてはいけないこと
- 入国時は、港・空港から特定技能所属機関まで送迎があること
- 住居確保の支援をすること
- 受入れ機関へ、業務や日常生活に関する相談・苦情を申し出ることができること
- 支援担当者の氏名及び連絡先 など
出入国送迎の支援
- 入国時の空港から住居までの送迎
- 帰国時の空港保安検査場までの同行
これらは特定技能外国人の失踪や不法滞在を防ぐためにも必要な業務です。
住宅確保・生活に必要な契約支援
特定技能外国人の住居に関して、以下のいずれかの支援を行う必要があります。
- 特定技能外国人が賃貸契約を結ぶ場合、不動産仲介業者や賃貸物件の情報を提供し、必要に応じて物件探しをサポート(同行含む)する
- 受入れ機関などが賃貸契約を結び、特定技能外国人の合意のもと住居として提供する
- 受入れ機関が所有する社宅を、特定技能外国人の合意のもと住居として提供する
また、受入れ機関または登録支援機関は、特定技能外国人が日本での生活をスムーズに始められるよう、以下の支援を行う必要があります。
- 銀行口座や貯金口座の開設
- 携帯電話の契約手続き
- 電気・ガス・水道などのライフライン手続き
必要に応じて、窓口案内や書類準備のサポート、外国人への同行支援もあります。
生活オリエンテーション
入国後の生活オリエンテーションでは、以下の情報を提供する必要があります。
- 金融機関の利用方法
- 交通ルールや公共交通機関の利用方法
- 医療機関の受診方法、医療通訳・民間医療保険の案内
- 生活ルール・マナー、生活必需品の購入方法
- 違法行為の例、トラブル時の対応・身を守る方法
- 災害情報の入手方法、避難指示や避難場所の把握
- 社会保障・税関連手続き、行政手続き全般
- 住宅地や所属機関に関する届出
- 労働関係法令・入管法令の基礎知識と違反時の相談窓口
- 人権侵害や労働契約違反に関する相談窓口
- 年金の受給資格や脱退一時金制度の概要と相談先
- 相談・苦情対応の支援担当者や関係機関の連絡先
このオリエンテーションは、十分に内容を理解できる言語で行います。特定技能外国人の母国語のほか、日本語でも本人が十分に理解できるのであれば問題ありません。8時間以上の実施が基準となります。
実施後は、「生活オリエンテーションの確認書」を配布し、特定技能外国人の署名を取得します。これが、オリエンテーションを受けた証明となります。
公的手続きへの同行
日本のルールや言語の壁により、外国人本人が手続きできない場合は、必要な支援を行います。
- 在留カード、住民登録などの手続き支援
- 必要書類の作成補助
日本語学習支援
登録支援機関は特定技能外国人に対し、以下のいずれかの支援を提供する必要があります。
- 就労・生活地域の日本語教室や日本語教育機関の入学案内情報の提供
- 自習用の日本語学習教材やオンライン講座の情報の提供
- 特定技能外国人の合意のもと、日本語教師と契約し、日本語講習を実施
特定技能外国人が日本での就労や生活に支障をきたさないよう、継続的な学習機会の提供が求められます。
相談・苦情対応
特定技能外国人から以下に関する相談や苦情を受けた場合、内容に応じた助言や指導を行う義務があります。
- 日常生活における相談対応
- 必要に応じた行政機関への案内
相談や苦情への対応として、必要に応じて適切な機関(地方出入国在留管理局、労働基準監督署など)を案内し、外国人に同行して手続きの補助を行うことが求められます。
また、相談しやすい環境を整えるため、平日3日以上、さらに土曜・日曜のうち1日以上対応し、就業時間外でも相談を受け付けられる体制を整える必要があります。
対応を行った際には、相談記録書に記録を残し、関係行政機関への相談や通報を行った場合には、支援実施状況の届出書に記載することが義務付けられています。
日本人との交流促進
特定技能外国人の日本社会への適応をサポートするために、以下のような支援を行うことが求められています。
- 地域のイベントや交流会などの情報を特定技能外国人に提供し、参加を促すこと
- 自治会などの地域コミュニティに特定技能外国人を紹介し、溶け込めるようにサポートすること
- 特定技能外国人が働いたり生活したりする地域の行事への参加を呼びかけること
これらの支援を通じて、特定技能外国人が日本人と交流する機会を持てるようにすることが、登録支援機関の重要な役割となっています。
また、各行事への参加にあたっての注意点や参加方法なども、丁寧に説明することが求められています。
転職支援(人員整理等の場合)
特定技能所属機関が人員整理などの理由により特定技能外国人との雇用関係を終了する際には、以下のいずれかの方法で特定技能外国人の次の就労先確保のためのサポートを行わなければなりません。
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝い
- 推薦状の作成等
- 求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
また、上記のサポートに加えて、以下の支援も必ず実施しなければならないため確認・実施の必要があります。
- 離職時に必要となる各種行政手続き(国民健康保険や国民年金の手続きなど)に関する情報を提供すること
このように、特定技能外国人との雇用関係が終了する場合でも、その後の就労先確保に向けて手厚いサポートを行うことが求められています。
定期的面談・行政機関への通報
特定技能外国人の適正な就労環境を確保するために、特定技能外国人の上司や雇用主などの監督的立場にある者と定期的な面談を行わなければなりません。
この面談は、少なくとも3ヶ月に1回以上の頻度で実施することが求められています。
面談の際に、以下のような問題が認められた場合には、関係行政機関への通報が義務付けられています。
- 労働基準法やその他の労働関連法令、入管法の違反
- 旅券や在留カードの不当な取り上げなどのトラブル
面談は、特定技能外国人が内容を十分に理解できる言語で行うこと。面談後には、「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成し、記録を残すことが必要とされています。
このような定期面談を通じて、特定技能外国人の就労状況を適切に把握し、問題があれば速やかに対応することが、特定技能所属機関や登録支援機関の重要な責務といえます。
特定技能外国人が安心して働ける環境を整えるために、面談を活用した丁寧なフォローアップが求められているのです。
上記の義務的支援以外にも、登録支援機関によっては以下のような任意のサポートサービスがあります。
- 支援計画作成支援
- 通訳派遣
- キャリアカウンセリング
- メンタルカウンセリング
- マナー講座
参考:厚生労働省 「特定技能外国人を受け入れる際のポイント」出入国在留管理庁
3.登録支援機関は必要?自社対応との比較と最適な選び方

特定技能外国人の支援は自社で完結させることも可能です。しかし、どんな場合に支援機関が必要で、どんな場合に自社対応が可能なのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、最適な選択方法を解説します。
絶対に支援機関が必要なケースとは?
以下のケースでは、登録支援機関への委託が必須となります。
外国人労働者の受入れ実績がない場合
- 直近2年間の受入れ実績がない企業は委託必須
- 生活相談に従事した経験のある職員がいない場合も必須
支援体制が整っていない場合
- 義務的支援を実施できる体制がない
- 特定技能外国人が内容を十分に理解できる言語に対応可能な人材がいない
初めて外国人労働者の受け入れを行う企業にとって、特定技能所属機関としての要件を満たすことは容易ではありません。そのため、多くの場合、外国人労働者への支援業務を専門の機関に委託することが不可欠です。
また、支援計画を特定技能外国人が内容を十分に理解できる言語で説明する必要があります。
実際のところ、このような専門的な業務に対応できる人材を自社内で確保することは、多くの企業にとって現実的ではありません。
特に、外国人労働者の受け入れが初めての企業では、社内にノウハウが蓄積されていないことが多いため、専門機関への委託が最も効果的な選択肢となるでしょう。
専門機関に支援業務を委託することで、外国人労働者に対して質の高いサポートを提供できるだけでなく、企業側の負担も大幅に軽減することができます。
これにより、企業は自社の本業に集中しつつ、外国人労働者の受け入れを円滑に進めることが可能になるのです。
自社対応できる条件をチェックしてみよう
自社での対応が可能となる条件は以下の通りです。
- 過去2年間の外国人受入れ実績がある
- 支援責任者・支援担当者を設置できる
- 特定技能外国人が内容を十分に理解できる言語で意思疎通が可能
- 支援計画を適切に実施できる体制がある
これらが整っていれば、登録支援機関に委託せずとも内製だけで問題はありません。
一部だけ支援を依頼するのはアリ?部分委託のメリット・デメリット
全ての支援業務を丸ごと委託するか、全て自社で行うか――。実はこの二択だけではありません。
自社でできる部分は自社で、自社の人的リソースでは対応が難しい部分のみを委託するという方法も可能です。
部分委託のメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。
メリット
- 必要な部分だけを外部委託でき、コストを抑制できる
- 自社の強みを活かしつつ、弱みを補完できる
- 段階的に支援体制を構築できる
デメリット
- 責任の所在が不明確になるリスク
- 情報共有や連携に手間がかかる
- 支援の一貫性が失われる可能性
部分委託は、自社の状況に応じて柔軟に活用できる選択肢です。
ただし、責任の所在や情報共有の手間などのデメリットもあるため、委託する業務の選定には慎重な判断が必要です。
自社の体制や予算を考慮しながら、強みを活かせる業務は内製化し、専門性の高い業務は委託するなど、バランスの取れた支援体制を目指しましょう。
4.登録支援機関の費用相場は?

登録支援機関の費用は機関によって様々ですが、一般的に以下の項目で構成されています。
支援項目ごとの支払いの場合
| 支援項目 | 相場 |
|---|---|
| 事前ガイダンス | 20,000~30,000円 |
| 生活オリエンテーション | 20,000~30,000円 |
| 出入国時の送迎 | 10,000~30,000円 |
| 住居の調査・確保・手続き支援 | 10,000~30,000円 |
| 日本語学習の支援 | 10,000~30,000円 |
| 銀行口座開設や携帯電話の契約などの支援 | 10,000~30,000円 |
| 医療機関への同行支援 | 20,000~30,000円 |
| トラブルや苦情対応の支援 | 10,000~20,000円 |
| 定期面談や相談の実施 | 10,000~20,000円 |
月額の場合
特定技能外国人1人当たりの支援委託料は、料金体系が全国で統一されているわけではなく、各機関ごとに異なります。
特定技能制度は比較的新しく、支援委託の相場はまだ安定していませんが、概ねの目安としては20,000~25,000円の金額帯が多いです。
5.失敗しない!登録支援機関の選び方のコツ

失敗しない支援機関選びのために、経験豊富な専門家が重要なチェックポイントとその確認方法を解説します。
法令を遵守しているかどうかをしっかりチェック
残念ながら、一部の登録支援機関では法令遵守が徹底されていない事例があります。それを見極めるためには選定する前に以下の内容を把握しておきましょう。
法令違反の事例
- 対応言語を増やすために、雇用関係のない者の名前だけを借りて、実際はすべて日本語で対応するケース
- 支援料金が非常に安い登録支援機関の中には、義務となっている支援すら行っていないところがある
もし登録支援機関が法令を遵守していなかった場合、以下のようなリスクが考えられます。
| リスク | 影響 |
|---|---|
| 登録支援機関の登録取り消し | 急遽別の機関を探す必要が生じる |
| 外国人材の受け入れへの影響 | 円滑な受け入れが困難になる可能性がある |
このようなトラブルを避けるために、登録支援機関を選定する際は最初に支援担当者が誰なのかを確認し、その方の対応言語を直接確かめることをおすすめします。
法令遵守は登録支援機関の基本中の基本です。外国人材の受け入れを円滑に進めるためにも、登録支援機関の法令遵守状況については、しっかりとチェックしておきましょう。
登録支援機関の比較ポイントは?後悔しない選び方
登録支援機関を選ぶ際の比較ポイントは、大きく「サービス内容」と「組織体制」の2つの観点から評価する必要があります。
サービス内容
サービス内容については、支援メニューがどこまで具体的に示されているかを確認しましょう。
「外国人支援」という漠然とした表現ではなく、事前ガイダンスの具体的な実施方法や、生活支援の詳細な内容など、明確な説明があることが重要です。
また、対応可能な業務範囲が自社のニーズと合致しているか、緊急時のサポート体制は整っているかなども、重要な確認ポイントとなります。
組織体制
組織体制については、担当者の専門性を重点的にチェックします。在留資格の専門知識を持つ行政書士や、外国人支援の経験が豊富なスタッフが在籍しているかどうかは、支援の質に直結することです。
また、担当者が急に休んだ場合のバックアップ体制や、入国管理局や自治体などの関係機関とのネットワークも重要な判断材料となります。
選定の際は、これらのポイントについて具体的な事例を交えて質問し、相手の回答の具体性や説得力を評価することをお勧めします。曖昧な回答や、実績の提示を避けるような対応があれば、やめておいたほうがいいでしょう。
適正価格の見極め方と予算の決め方
登録支援機関の費用は、初期費用から月額費用まで様々な項目があり、一概に「高い・安い」の判断が難しいものです。
支援の質を担保しながら、どのように適正な価格を見極め、予算を設定していけばよいのかを、実務経験に基づいた具体的なポイントをお伝えします。
複数の機関から見積もりを取得
登録支援機関の適正価格を見極めるためには、まず複数の機関から見積もりを取得することから始めましょう。少なくとも3社以上の比較検討が推奨されます。
その際、単純な価格の比較だけでなく、提供されるサービス内容を詳細に比較することが重要です。
見積もり評価のポイントは主に以下の3つです。
- 初期費用と月額費用の内訳が明確になっているか
- 追加料金の有無とその内容
- 提示された価格が支援内容と見合っているか
緊急対応時の追加費用や、通常業務範囲を超える支援が必要になった場合の料金など、予期せぬ出費が発生する可能性がある項目については、事前に確認しておく必要があります。
さらに、提示された価格が支援内容と見合っているかの評価も重要です。
予算を決める際は、自社の受入れ規模や必要なサポートの程度を考慮しながら、適切な金額を設定していきましょう。また、予期せぬ事態に備えて、ある程度の予備費を確保しておくことをお勧めします。
最後に、契約前には必ず見積書の内容を詳細に確認し、不明な点があれば質問するようにしましょう。価格の内訳や支援内容について、口頭での説明だけでなく、書面での確認を怠らないようにするのがポイントです。
これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます
6.登録支援機関についてよくある質問
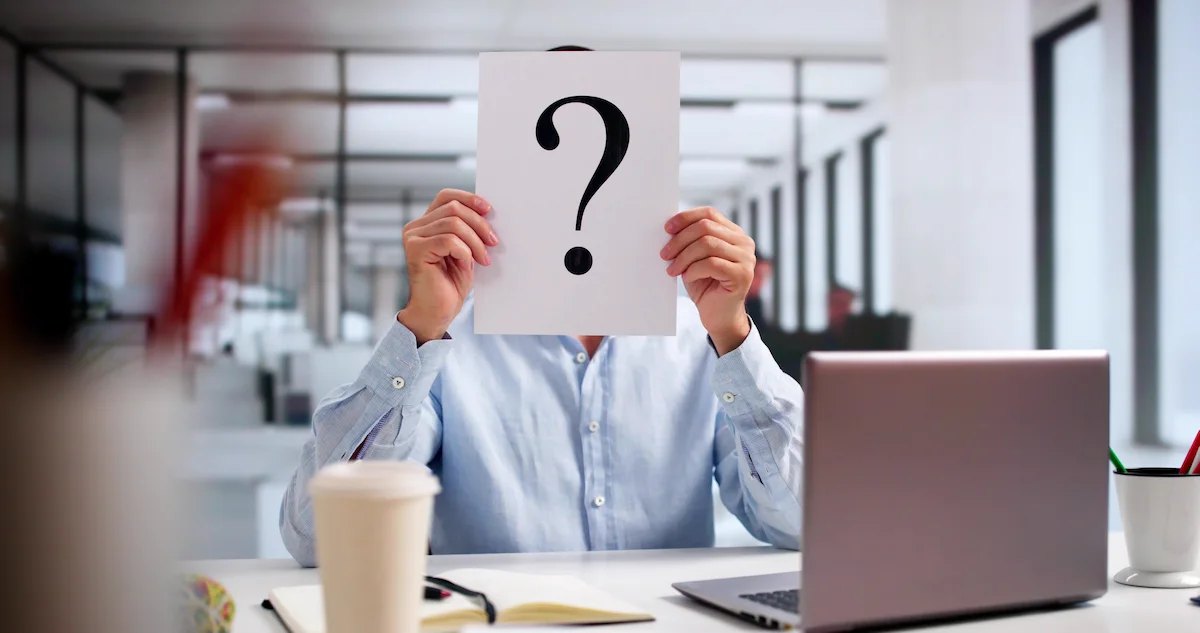
実際に登録支援機関の利用を検討する中で、多くの企業が抱える疑問や悩みについて、Q&A形式でお答えします。
費用を抑える工夫や、支援機関を利用している企業の実態など、具体的な事例も交えて解説します。
Q1. 登録支援機関を利用すべき企業とは?受入れ実績なしでも大丈夫?
初めて外国人材を受け入れる企業の場合、特定技能所属機関としての要件を満たすのは難しいかもしれません。
でも、そのような場合は登録支援機関に支援業務を委託することで、スムーズに外国人材を受け入れることができます。
登録支援機関は主に以下に該当する企業が利用しています。
- 初めて特定技能外国人を採用する企業
- 支援体制の整備が難しい中小企業
- より効率的な外国人材活用を目指す企業
- 多国籍の外国人材を受け入れている企業
Q2. 登録支援機関の費用を抑える方法はある?
登録支援機関を利用する際の費用が気になりますよね。でも、ご安心ください。費用を抑えるためのいくつかの方法があります。
- 支援計画は自社で作成するなど、できる範囲の業務は自社で対応する
- 支援業務の一部のみを登録支援機関に委託する
- 複数の登録支援機関から見積もりを取り、比較検討する
- 外国人材の人数や業務内容によって、登録支援機関と費用の交渉をする
このように、自社でできる部分は自社で対応し、必要な部分のみを登録支援機関に委託することで費用を最小限に抑えることができます。
また、複数の登録支援機関から見積もりを取ることで、最も自社に合った費用プランを選択することも費用削減には有効です。
外国人材の受け入れ規模や業務内容によっては、登録支援機関と費用の交渉をすることもできます。
登録支援機関は、外国人材の受け入れを支援することが本来の目的ですから、企業の事情を理解してくれる可能性が高いでしょう。
費用面で不安を感じることもあるかもしれませんが、様々な方法を検討することで、自社に合った最適な方法を見つけることができます。
特定技能の定期報告も自社で行いたい場合は、こちらの記事に詳しくまとめられているためおすすめです。
7.登録支援機関とのパートナーシップで、外国人材受け入れを成功へ

登録支援機関の活用は、特定技能外国人の受入れを成功に導く重要な要素の一つです。
自社の状況を適切に判断し、必要な支援を見極めることで、効率的な外国人材の活用が可能になります。
本記事で解説した選定のポイントと連携のコツを参考に、貴社に最適な支援体制を構築し、Win-Winの関係を築いていただければ幸いです。



















